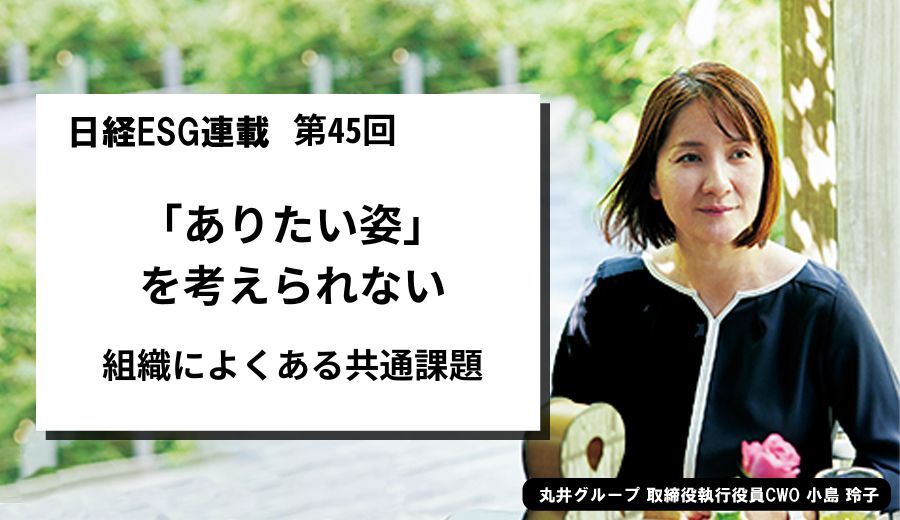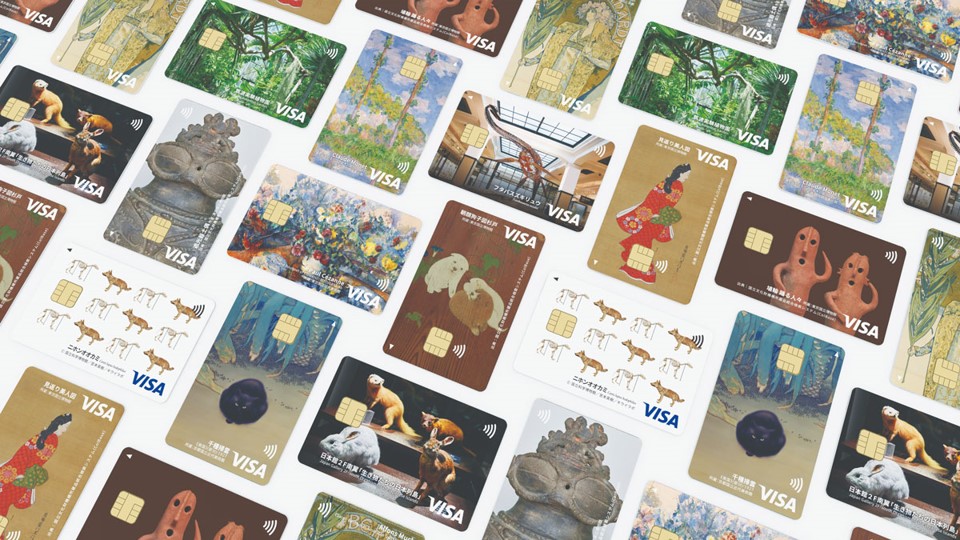「正解」への依存

経営に欠かせない要素として「ウェルネス」や「Well-being」が注目されています。不確実性が高まっている世の中で企業が生き抜くためには、心身ともに健康でイキイキと働く社員を増やすことが大切です。社員の病気やケガを予防するだけにとどまらず、創造性を引き出し、生産性を高めるWell-being経営とは何か。 産業医と取締役執行役員の2つの顔を持つ丸井グループの小島玲子氏が解説します。 出典:「日経ESG」連載「『しあわせ』が企業価値を高める ウェルビーイング経営のススメ」より
受験勉強のように、「正解へのハウツー」に依存する価値観は根強い。人の創造性を高めて企業価値につなげるには、未知の領域への探求心を育む必要がある。
教師が正解の出し方を説明し、生徒がそれを暗記してテストに臨む。そうした日本の教育の影響を感じる場面が時々あります。
丸井グループでは2023年、「フロー状態に入れる組織文化」という方針と数値目標を示しました(本連載第37回)。すると社内では、フローについて勉強する人が増えました。約20年前から人と組織の活性化の鍵がフローだと考え研究してきた私は、うれしく思いました。しかし次第に違和感も覚えるようになりました。「フローの定義をまだ言えないので、早く覚えます」「フローに入れるよう努力します」という話や、「どうすればフローに入れますか」「手っ取り早い方法はありますか」といった方法論に関する質問を耳にするようになったからです。
フローとは主体的に行為に没頭し、自我意識が飛んでいる状態です。決められた目標の達成のためにフローに「入らなければならない」という義務感や、方法論(ハウツー)を意識すればするほど遠ざかるのが、フロー状態です。
ありたい姿に向かって創意工夫し、正解のない世界に自ら歩み出して創造性を発揮する企業文化へ──。その変革の象徴としてのフローという概念に対して、「方法論を駆使して与えられた目標達成のために努力する」という従来の仕事の価値観で臨んでいたと言えます。
19世紀の数学者ガウスは、「知識ではなく学ぶ行為こそが、所有ではなくそこにいたる行為こそが、最も喜びを与えてくれる」と言ったとされます。この言葉はフロー状態の本質を表していると思います。ガウスは目標の達成や功績を残すためではなく、数学そのものが好きで没頭していました。そして結果的に数々の功績を残し、史上最高の数学者とも呼ばれるにいたったのです。
一生懸命タイプの弊害
実のところ私は、ウェルビーイングやフローを全社方針に掲げるからといって、学校のようにその言葉の定義を教えて、社員が言えるようになる必要はないと考えています。
自分が好きなことに没頭し、ある日フローについて聞いた時に「ああ、それは私のことですよ」と言える人が増えればそれで良い。「ウェルビーイングの定義はわからないけれど、私の職場では皆イキイキ仕事をしています」と言える人が増えれば、それで良いのです。大事なのは、ビジョンやありたい姿に近づいているかどうかです。
未来のビジョンやありたい姿がないと、「何をやって、何をやらないか」の優先順位付けもできません。往々にして目の前に来た仕事を「全部やる」状況になり、やたらと忙しくなります。
英ロンドン・ビジネススクール教授を務めたスマントラ・ゴシャール氏は、複数の企業の経営層やマネジャーを研究し、その行動タイプを4つに分類しました。同氏は著書*¹で、全部やろうとする、すなわちエネルギーは高いが集中力の低い「一生懸命タイプ」のマネジャーは、エネルギーの低い人よりも組織にとって有害と述べています。
*¹ 『意志力革命 目的達成への行動プログラム』(ハイケ・ブルック、スマントラ・ゴシャール著、野田智義訳/ランダムハウス講談社)

経営学者スマントラ・ゴシャール氏らによる研究。パーセンテージは該当したマネジャーの割合を示す
(出所:『意志力革命 目的達成への行動プログラム』(ハイケ・ブルック、スマントラ・ゴシャール著、野田智義訳/ランダムハウス講談社)をもとに筆者作成)
このタイプの人は意欲があり、仕事熱心で善意の持ち主。毎日おびただしい量の課題に気を奪われています。どの仕事も急を要すると感じて優先順位をつけられません。その結果、近視眼的で衝動的な行動を取りがちです。時間を取って内省や振り返りをしないため、異なるプロジェクトにいくつも首を突っ込むなど非効率な行動パターンを取りやすいと言います。
この研究ではマネジャーの40%がこのタイプという結果でした。私は長年産業医として管理職の不調事例に多く接する中で、「一生懸命タイプ」のマネジャーの割合は日本ではもっと高いのではないかと推測しています。
一方、エネルギーも集中力も高い「目的意識タイプ」は、困難な状況でも未来のありたい姿に向かって最も重要なこと柄は何かを考え、それにフォーカスして行動する人です。このタイプの人が未来の価値をつくるとゴシャール氏は言います。しかし、そもそも組織で未来のありたい姿が描けていなければ、マネジャーが未来志向で考え、こうした行動を取ろうとすること自体が難しいでしょう。
探求する力を育む
未来のありたい姿を描き、それに向かって不確実な世界に歩み出すのは、個人でも組織でも難しい。誰かに、「こうすればいいのです」という正解を示してほしい。その規範に従ってさえいれば、人生がうまく回るようにしてほしい。いつの時代も、そうした欲求が宗教を生み出す原動力の一つとなっているのでしょう。
私には特段の宗教心がないので、人々にこうした「正解」を与えるのが宗教だと考えていたところ、真宗大谷派住職の瓜生崇氏が、著書*²で「本当の宗教とは、人々に『迷う力』を与えるものである」と述べているのに感銘を受けました。「宗教として何が正しく、何が間違っているのかという判断基準に普遍的な真理は存在しない」と、同氏は言います。
企業組織においても、正解のない問いを立てて皆で対話を重ね、「迷う力」を付けていく必要があると私は思います。そうすることで少しずつ、ガウスのように行為そのものに喜びを感じながら、未知の領域を探求する人が増えていくのではないでしょうか。
*² 『なぜ人はカルトに惹かれるのか 脱会支援の現場から』(瓜生崇著/法蔵館)