#016 ダイアローグ
対立から共生へ、議論から対話へ

デヴィッド・ボーム(著)、金井 真弓(訳)
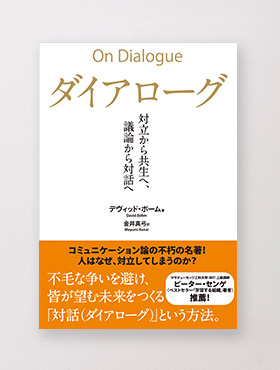
「人間は、結局、自己正当化しないと生きていけないのかな?」
友人のF君が独り言を言うような口調で、私に問いかけた。
大学に入学した年の春、授業が終わって昼食に向かおうとしていた時だった。
唐突な問いに不意を突かれたこと、そして、F君がどんな理由でこんなことを聞いたのかを測りかねて、僕は思わず押し黙ってしまった。
そのまま、この問いは答えられることなく、心の中にしまい込まれた。
それ以来、ふとした拍子にF君の言葉を思い出すことがあった。
早熟の天才だったF君のことだから、私には想像もつかないような深遠な理由があって、こんな難しいことを考えていたのだと思うが、何度思い返しても、この問いに満足のいく答えを与えることはできなかった。
そして、それは再び眠りにつくように、心の引き出しに仕舞い込まれるのだった。
人生にはこんなふうに、長く心の中に残り、棲みついてしまう言葉がある。
それは、やがて「誰か」の言葉ではなく、自分自身の言葉であるかのように、その人の一部になってしまう。
デヴィッド・ボームによると、人間の思考は「想定」を生み出し、想定は「意見」を生み出す。
「想定」は、物事の見方や世界の理解の仕方で、誰もが持っている。
この「想定」に基づいて「意見」が生まれる。
人はさまざまな意見を持つようになるが、それらが時間を経て、経験などに裏打ちされることで確固としたものになると、人は自分自身と自分の意見を同一視するようになる。
そうなると、人は自分の意見に異議を唱えられると、あたかも自分自身が攻撃されたかのように感じて、自分を守ろうとする。
自分を守るために、人は感情的になり、相手を攻撃することもある。
これが「自己正当化」のメカニズムだ。
ボームは、このメカニズムは人間の本能のようなもので、ジャングルに足を踏み入れた者が危険な動物から身を守ろうとする自衛のメカニズムと同じだと言う。
しかしながら、自己正当化は危険性も孕んでいる。
誰もが自分の意見に固執し、譲ることはできないと感じ始めると、人は衝動のままに行動するようになり、そこから「対立」が生じてくるからだ。
個人と個人の対立だけでなく、国家間や民族間、宗教間の対立も「譲ることのできない」想定や意見から生じる。
また、環境問題も人間と地球環境の「対立」から生じている。
人間が生きていくうえで避けられない自己正当化と、その結果として招いてしまうさまざまな対立という矛盾を解決するための道はあるのだろうか。
対立を乗り越えて共生へ進む道を示すのは「対話」である、とボームは言う。
私たちは対話を通じて、誰もが心の底では無意味だと感じている不毛な争いを避け、本当に意味のある未来へと向けて歩むことができる。
誰もが望む未来をつくるための方法が「対話」なのだ。
ボームはさまざまな観点から対話の理論と実践について考察している。
その観点は実に多様で、奥深く、想像力をかき立てる。
そのほんの一部を紹介する。
まず、語源を辿ると、対話(dialogue)は、ギリシャ語のdia-logosで、「言葉を」「通して」という意味らしい。
これに対して、議論(discussion)の語源は、「打楽器(percussion)」と同じで、物事を叩いて壊すという意味があるという。
ボームは、言葉を表すlogosという語を、もう少し広げて「意味」と捉え、対話の語源は「意味の流れ」である、としている。
それは「二つの岸の間を流れる川のように、意味が間を通り移動していく、人と人の間の自由な意味の流れ」のようなものだという。
この比喩はとても興味深い。
おそらく「二つの岸」は対立を象徴していて、川はその対立を超える領域を示している。
そして、「意味の流れ」は「何か新たな理解が生まれてくる可能性」を示す創造的なものである。
それは「何かの意味を共有することで、人や社会を互いにくっつける役割」、「接着剤やセメント」のようなものだという。
さらに興味を惹かれるのは、この「意味の流れ」が集団的で暗黙的なものだという主張である。
対話は基本的に個人ではなく、集団、グループにおいて実践される。
その実践にあたっては、いくつかの原則がある。
例えば、対話では議論と違って特に目的を定めず、いかなる結論も求めない。
重要なのは、自分の意見に固執して人の意見を否定したり、
自分の意見を押し通すことで議論に勝とうとする態度を捨てること。
つまり自己正当化しないことである。
そのために、ボームは対話においては自分の意見を「保留状態」にすることを推奨している。
自分の意見やその元となる想定をいわばカッコに入れて、判断を一時的に中断してみること。
それによって、相手の意見に対する自分の気持ちや自分の反応を「鏡を見るように、自ら観察、検討してみる」のである。
他人が自分に与える影響を鏡のように見、自分が他人に与える影響を鏡のように見ること。
対話グループがお互いにとっての鏡の役割を果たすことで、思考のプロセスをより繊細に見つめられるようになり、個人の意見に執着しようとする本能を回避することができる。
グループ内の友好的な感情が維持されることで、誰もが話すことができ、どんな内容も排除されない自由なコミュニケーションができるようになってくると、個々の意見の対立を超えた「共通の意味」が暗黙の領域から生まれてくる。
その時、「共通の意味」はおそらく「真実」というものを示す。
グループ内の誰もが共有できる真実である。
そして、真実が「暗黙の領域」から生まれてくる、ということも極めて興味深い。
ボームは「真実は意見からは生まれない、暗黙的な心のより自由な活動から生まれる」と言っている。
「暗黙の領域」はマイケル・ポランニーの「暗黙知」と同じと考えてよいだろう。
野中郁次郎先生の「暗黙知」とも通じている。
暗黙知は言語では表せない知であり、身体的な知を含む。
それは、言語の背景にあって、私たちの日常の行動や思考を可能にしている基盤であり、
また、創造性の源泉でもある。
ボームはこの暗黙知に個人を超えた集団的な性質を認めているようだ。
私たちは対話を通じて、個人を超えた暗黙知の領域に合流していく。
そこでは、私たちは「結局のところ、人は皆同じなのだということに気づき」、その結果
「感情を共有し友情を育むことで、よりオープンになり互いを信用する」ようになる。
そのような状況から隠されていた「真実」が見出され、真の「知性」が働き出す。
このような知性が「世界の状況を変えるための突破口になる」という。
対話は、ボームによると古代ギリシャで尊ばれた非常に古くからある考え方だが、残念ながら現代においては失われたも同然になっている。
しかしながら、今でもかろうじて対話の文化を継承している人たちもいる。
ボームが紹介しているのは、北アメリカの先住民の事例である。
それは、はるか昔に人類が実践していたとされる「対話」が、どのようなものだったのかを示す最もシンプルで、美しい事例だと思われるので、最後にそのくだりを引用する。
「かつて、北アメリカのある部族と長い間暮らしを共にした人類学者がいた。それは50人弱からなる、小さな部族だった。(・・・)その部族はときどき寄り合いを持つことがあった。彼らはただひたすら話すだけで、何の目的もなく話しているのは明らかだった。そこではどんな決定もなされなかった。その中にリーダーもいない。そして誰もが参加できた。
(・・・)会合は長々と続き、やがてまったく何の理由もなしに終わって、集まりは解散する。だが、そうした会合のあとでは、誰もが自分のなすべきことを知っているように見えた。というのも、その部族の者たちは互いを充分によく理解したからである。そのあと、彼らはより少人数で集まって、行動を起こしたり、物事を決めたりするのだった。」(下線は筆者)
私たちは、このような「対話」を現代社会において復活させ、実践することが果たしてできるだろうか。
少し気が遠くなるような気もする。
だが、この部族が実践していることを理解し、そのことに共感できる感受性が私たちにあるとしたら、対話の可能性は拓けていると思う。
ガンジーは「よいものはカタツムリのように進む」と言っている。
対立から共生への道は険しいかもしれないが、私たちは対話を実践することで共生へと歩みを進めることができる。
















